過剰担保
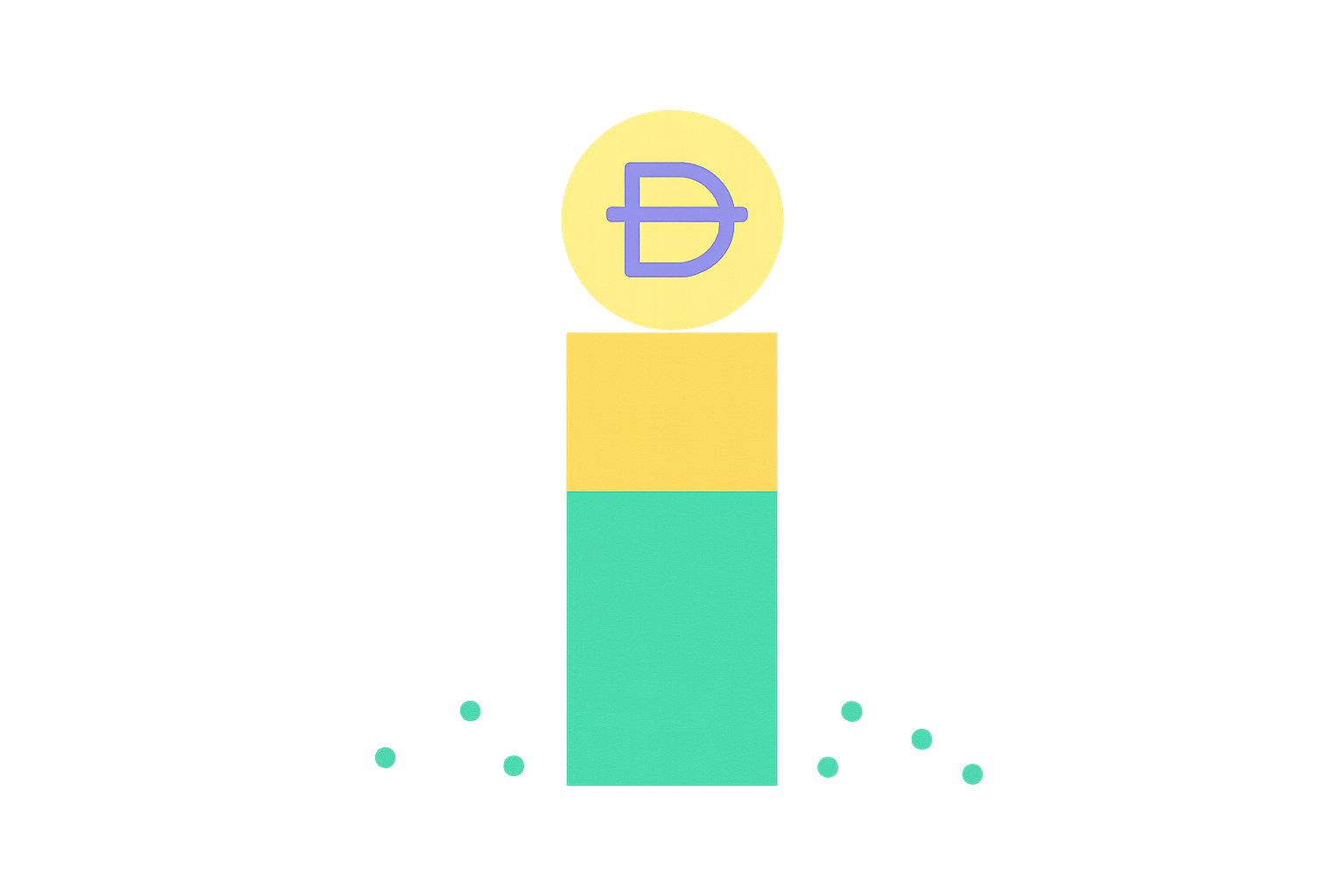
オーバーコラテラリゼーションとは
オーバーコラテラリゼーションとは、借入額を上回る資産を担保として差し入れることです。
暗号資産レンディングやステーブルコイン発行の分野では、オーバーコラテラリゼーションは負債額よりも高い価値の担保を提供することを指します。これにより価格変動への耐性が生まれ、清算リスクが低減されます。特に価格変動の大きい資産を対象とする暗号資産レンディングプロトコルや取引所の借入で広く採用されています。
担保率(コラテラリゼーションレシオ)は、借入額と担保価値の比率です。担保率が低いほど安全マージンが大きくなります。例えば、担保率70%なら100ドル相当の担保で最大70ドルを借りることができます。
清算閾値(リクイデーションスレッショルド)は、担保が強制的に売却される基準点です。担保価値が下落し担保率がプロトコルの設定値を超えると、清算が実行されます。
ヘルスファクターは、一部プロトコルでポジションの安全性を示す指標で、値が高いほど安全性が高まります。1を下回ると清算のリスクが高くなります。
オーバーコラテラリゼーションが重要な理由
オーバーコラテラリゼーションは、借入可能額、金利コスト、清算リスクを直接左右します。
価格変動の激しい市場では、借入額より多く担保を差し入れることで安全マージンが広がり、ポジションの安定性が増しますが、その分資本が拘束され、機会コストも生じます。これを理解することで、適切なレンディングプラットフォームや担保資産の選定が可能となります。
例えば、Gateで現物資産を担保に借入する場合、各資産ごとに最大ローン・トゥ・バリュー(LTV)比率が設定されています。価格変動の大きいトークンは高いオーバーコラテラリゼーションが必要となり、安定資産は要件が緩和されます。担保選択を誤ったり、担保率を上げすぎると、価格下落時に清算リスクが高まります。
レバレッジ取引やアービトラージを行う場合も、適切なオーバーコラテラリゼーションは強制清算のリスクを抑え、戦略の持続性を高めます。
オーバーコラテラリゼーションの仕組み
オーバーコラテラリゼーションは、「担保評価→担保率設定→継続的な監視→必要時の清算」という流れで運用されます。
ステップ1:担保価値の評価。プロトコルや取引所は、プライスオラクルや現物価格を使い、担保の市場価値を算出します。
ステップ2:担保率と清算閾値の設定。担保率は最大借入限度を定め、清算閾値はその下にバッファとして設けられます。
ステップ3:価格とポジションの継続監視。システムはヘルスファクターをリアルタイムで計算し、リスクが高まると警告や追加借入の制限を行うことがあります。
ステップ4:必要時の清算。価格下落でヘルスファクターが1に近づいたり担保率が閾値を超えた場合、システムが担保を売却して負債を返済します。
例:1 ETHを担保にステーブルコインを借りる場合、ETH価格が3,000ドルでプロトコルが150%のオーバーコラテラリゼーション(最大担保率66%)を要求する場合、約2,000ドルまで借入できます。ETH価格が2,400ドルに下落すると担保率は2,400/2,000=120%。清算閾値が120%なら清算間近となり、追加担保や一部返済が必要です。
暗号資産領域でのオーバーコラテラリゼーション活用例
オーバーコラテラリゼーションは、ステーブルコイン発行、レンディング、マージントレード、NFTレンディングなどで広く利用されています。
- MakerDAOのマルチコラテラルボールトでは、ETHやステーキングETHなどを担保にDAIを発行します。担保率は130%~170%で、価格変動の大きい資産ほど高い比率が求められます。
- Aaveのようなレンディングプロトコルでは、ETHやBTCのLTV比率は70%~80%(オーバーコラテラリゼーション125%~143%)が一般的です。安定資産やトークン化国債は要件が緩和される場合があります。
- Gateの借入・マージン商品では、現物トークンやステーブルコインを担保に差し入れます。プラットフォームは資産のボラティリティに応じてLTVや清算閾値を調整し、価格下落時には自動的なポジション縮小やマージンコールが行われることがあります。
- NFTレンディングでは、ブルーチップNFTは価格や流動性の不確実性から高いオーバーコラテラリゼーションや短期ローンが求められます。
オーバーコラテラリゼーション要件を下げる方法
安定した担保資産の選定、ポジション構造の最適化、動的な管理戦略によってオーバーコラテラリゼーションを最適化できます。
ステップ1:堅牢な担保の選定。主要ステーブルコインや人気のステーキングトークンなど、低ボラティリティかつ高流動性資産を使うことで、通常は要件が緩和されます。
ステップ2:分散と構造化。相関の低い資産に担保を分散し、一つの資産の下落が全体に影響しないようにします。高ボラティリティ資産は別プールやアカウントで隔離し、リスクの波及を防ぎます。
ステップ3:安全マージンの維持とアラート設定。目標担保率を清算閾値より十分高く保ち、価格アラートや自動返済・担保追加機能を活用します。
ステップ4:リターンと手数料の最適化。ステーキング資産の利回りで金利コストを相殺し、低金利のプラットフォームや時期を選ぶことで借入コストを抑えます。
Gateでは、ステーブルコインや高流動性現物資産を主担保に利用したり、ポジションページでリスクアラートを有効化したり、ヘルスファクター低下時に優先して債務返済や担保追加を行うことで、強制清算を回避できます。
オーバーコラテラリゼーションの最新動向とデータ
過去1年で、主要プロトコルは資産ごとにリスクパラメータをさらに細分化しています。
2025年第3四半期のデータでは、主要レンディングプロトコルにおける高ボラティリティ資産のLTVは70%~80%(オーバーコラテラリゼーション約125%~143%)、安定資産は85%~90%(約111%~118%)が一般的です。詳細は各プロトコルのリスクパラメータを必ず確認してください。
2025年を通じて、一部プロトコルではステーブルコインやリアルワールドアセットが暗号資産担保全体の割合を拡大しています。より安定した裏付け資産へのシフトにより、オーバーコラテラリゼーション要件が緩和される傾向が見られ、価格変動やオラクルリスクの管理強化と関連しています。
直近6カ月間、取引所やレンディングプラットフォームは、自動担保追加、段階的リミット、隔離プールなどの自動リスク管理ツールを導入し、システミックな清算を抑制しています。ユーザーにとっても動的なポジション管理の重要性が高まっています。
2026年に向けては、高ボラティリティやロングテール資産は引き続き高いオーバーコラテラリゼーションが求められ、質の高い流動資産はより有利な条件が期待されます。プラットフォームのパラメータ更新や金利変動を注視し、資本効率とリスク管理の最適化が鍵となります。
オーバーコラテラリゼーション型レンディングと無担保レンディングの違い
両者は、利用要件、リスク管理、ユーザー層において大きく異なります。
オーバーコラテラリゼーション型レンディングは、担保資産を保証とし、借入額は担保額未満に制限。清算はスマートコントラクトにより自動で行われ、透明性の高いオンチェーン環境や一般ユーザーに適しています。
無担保レンディングは、借り手の信用力やビジネスのキャッシュフローを基準とします。主に機関投資家や実績ある借り手が対象で、プラットフォームが与信審査やクレジット枠管理を実施。オンチェーンの無担保信用も存在しますが、多くは機関向けで、個人はアクセス制限や分散によるリスク管理が行われます。
初心者は、オーバーコラテラリゼーションの仕組みを理解することでレンディングやレバレッジ商品を有効活用でき、無担保レンディングを利用する際はカウンターパーティリスクやプラットフォームのリスク管理体制を必ず確認する必要があります。
主要用語
- オーバーコラテラリゼーション:借入額を上回る価値の資産を担保に差し入れ、プラットフォームのリスクを低減する仕組み。
- スマートコントラクト:設定された条件を仲介者なしで自動実行するプログラム。自動レンディングや清算を可能にします。
- 清算:担保価値が閾値を下回った場合、プラットフォームが担保資産を自動売却し貸し手を保護すること。
- ガス代:ブロックチェーン上で取引実行時にユーザーが支払う手数料。
- フラッシュローン:1回のトランザクション内で借入と返済が完結する無担保ローン。
- リクイディティマイニング:流動性提供者が取引手数料やプラットフォーム報酬を獲得できるインセンティブ仕組み。
FAQ
妥当なオーバーコラテラリゼーション比率は?
資産の種類や市場のボラティリティによりますが、一般的に150%~300%が妥当とされています。例としてGateのレンディング商品では、ステーブルコインは低め(150%程度)、高ボラティリティ資産は250%~300%が必要です。適切な比率を選ぶことで、資産の安全性と担保活用効率のバランスが取れます。
オーバーコラテラリゼーションはリターンに影響するか?
はい。オーバーコラテラリゼーションは資本効率に直接影響します。担保比率が高いほど借入可能額が減りますがリスクは低下し、低い比率は資本活用を高めますがリスクも増加します。Gateで借入する際は、自身のリスク許容度を考慮してください。安全重視なら高比率(300%など)、積極運用なら低め(150%~200%)を選択できます。
担保が大幅に値下がりした場合は?
担保が急落すると担保率が悪化し、清算リスクが高まります。例えば150%で借入していた場合、担保が33%以上下落すると清算が発生する可能性があります。これを避けるには、アラート設定や早めの担保追加、価格下落前の一部返済が有効です。
全ての暗号資産が同じオーバーコラテラリゼーション要件か?
いいえ、資産ごとにボラティリティや流動性が異なるため要件も大きく異なります。USDTやUSDCなどのステーブルコインは120%~150%、BTCやETHは150%~200%、小型トークンや高リスク資産は250%~400%が求められる場合もあります。Gateでは各資産の要件を必ずご確認ください。
オーバーコラテラリゼーションとリスクの関係は?
低い担保比率(150%など)はリスクを高める一方、資本効率を高めます。高い比率(300%以上)はリスクを抑えますが、借入余力が制限されます。オーバーコラテラリゼーションは、より多くの担保を差し入れることで借入の安全性を確保する仕組みです。市場のボラティリティが高いほど、必要なバッファも大きくなります。市場状況と自身のリスク許容度を十分に考慮して比率を選択してください。
参考リンク
- https://www.investopedia.com/terms/o/overcollateralization.asp
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commercial-lending/overcollateralization/
- https://coinmarketcap.com/academy/glossary/over-collateralization
- https://www.wallstreetoasis.com/resources/skills/credit/overcollateralization
- https://www.poems.com.sg/glossary/financial-terms/overcollateralization/
関連記事

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?
